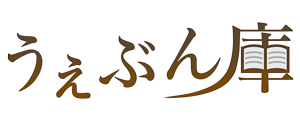記憶の中の桜は、いつも緑色だった。
「就職しないまま卒業した年に、こんな満開な桜を見ることになるなんてなぁ」
祖父母の家の庭にある、大きな桜の下に寝転び――映志(えいじ)は自分に語りかける。
鼻の上に舞い落ちた花弁を手に取り、太陽に透かすと、薄桃色の花越しに青空が見えた。
夢も希望も無くしてしまった映志にとっては、春の穏やかな光すら眩しくて仕方がない。
逃げるように目を閉じても、瞼の裏に浮かぶのは彼の将来を心配する両親の顔だ。
父に促されてすぐに祖父母の元で畑仕事を手伝うことになったが、実際に働いた結果、映志には向いていないことが初日の時点でわかった。
大学の四年間、不健康な生活を続けていたせいか早起きが辛いうえに、七十代の祖父母よりも体力がないのだからどうしようもない。
「数年ぶりに顔を合わせて、大きくなったねって喜んでくれたのに……最後は二人とも少しガッカリしてたな」
思い出は美化されるもので「まだ慣れていないだけで、本当はできる子だものね」などとフォローされたが、できる子ではなかったから彼は今ここにいるのだ。
このまま桜の下で眠り、いっそ目を覚まさなければ……などと危ない考えが浮かび、慌てて飛び起きると――
「きゃ!?」
「痛ぇっ!」
頭に鈍い衝撃が走り、再び地面に尻をついた。
目の前がチカチカと白く点滅する。
歯を食いしばり前方を確認すると、ピンク色のワンピースを着た少女が、映志と同じように尻もちをつき、ぶつけたと思われる頭を手で抑えていた。
「っ、誰だよアンタ。ここはうちの庭だぞ!?」
「ごめんなさい! 私は……えっと、ヨシノです。おじいさんとおばあさんに名前を言えば、分かってもらえると思います」
映志は頭の痛みに耐えながら、ヨシノの服装を黙って観察する。
彼女は鞄一つ持っていないうえ、古風なことに下駄を履いていた。
近所を散歩する程度の軽装だ。
申し訳なさそうに映志を見つめる瞳は、頭をぶつけたせいもあって若干潤んでいる。
怒鳴ってしまった罪悪感で、映志の苛立ちは急に萎んでしまった。
「……じゃあその、うちのじいちゃんばあちゃんと知り合いのヨシノさんは、なんで俺の顔を覗き込んでたんだ?」
「東京からお孫さんが帰って来たと聞いたので、様子を見に来たんです。声をかけようとしたら、ちょうど映志さんはお昼寝していたみたいで……ゴツンと」
「急に起き上がって悪かった。それにしても……まったく、近所でどんな噂話をされてるんだか」
ヨシノが、きょとんとした顔で映志を見つめる。
「ジッと観察するほど、田舎ではフリーターって珍しいのか?」
「今は畑仕事を手伝っているんですし、フリーターとやらではないと思いますけど……」
そこで言葉を区切り、ヨシノは柔らかい笑顔を見せた。
「それより私は、映志さんはまた演技が上手になったなぁって思いましたよ!」
「はぁ?」
「さっき一人で話していたのも、劇の台詞を練習してたんじゃないんですか? 真に迫っていてグッときました」
「あ、あれはただの独り言だ!」
「えっ!?」
映志が慌てて否定すると、今度はヨシノが驚く番だった。
彼女は驚きのあまり立ち上がり、その場を意味もなくうろうろと歩き回る。
「そんな! 映志さんは、役者の夢を諦めちゃったんですか……?」
「役者の夢?」
「だって昔……ほら、映志さんが小学生の時ですよ! 夏休みの暑い昼間、この桜の下でよく一人で遊んでいたでしょう? 一人で劇をして、大きくなったら演技をする仕事をするんだーって……」
映志が反応しないため、ヨシノの声はだんだんと自信なさげに小さくなっていく。
「……話してました、よね?」
祖父母の家に遊びに来た夏休み、すっかり花が散った桜の下で――
「……あぁ……うん。そういえば、してた……かも」
思い出した瞬間、まるで額をぶつけた時のように、映志の目の前がチカチカと白く点滅した。
歳の近い従兄弟がいなかったせいか、当時の映志は親戚の家に行くと一人で遊んでいることが多かったのだ。
劇というのも子供のおままごとのようなものだが、その様子を庭の外からでも見られていたのだろうか。
しかし、その頃ヨシノはまだ生まれてないのでは、と映志が疑問に思ったところで――
「私は、映志さんが就職しなかったっていうから、畑仕事を手伝いながら役者の勉強でもするのかと思ったんです」
「それは全く考えてもいなかった……」
「じゃあ、考えてみてください! 隣町には、演劇サークルもあるそうですよ! 勉強しようと思えば、いつどこでだってできるんです」
ヨシノの明るく力強い声を聞いていると、映志は眩しくて仕方なかった春の光が、まだ自分を見捨てていないように感じた。
彼女の肩越しに見える青空まで、たまらなく綺麗に見えるのだ。
両親や祖父母、友人や教授、周囲の人間に心配され過ぎたことで余計に疲れてしまった心が、癒されていくようで――
「私は、ずーっと映志さんが教えてくれた夢を応援していたんですから!」
ヨシノは笑顔で言いきると、そのまま下駄をカランコロンと鳴らして庭を出て行ってしまった。
映志の返事を聞かなくても、彼の表情を見て気持ちの変化に気づいたのだろう。
映志が桜の下でしばらくぼんやりしていると、祖母がやってきた。
「ちょっとそこまで、夕飯の買い出しをしてくるわね」
「それなら俺が行くよ。……それより、ばあちゃんはヨシノさんって知ってる?」
ふと、ヨシノが「祖父母に聞けば自分のことを知っている」と言っていたのを思い出したのだ。
「ヨシノさんは、うちの庭にいる……今、映志ちゃんが寄り添ってる桜のことよ。近所の人はみんなそう呼ぶの」
「えっ?」
「誰かに聞いたの? そういえば、昔は夏休みに遊びに来ると、よく桜の下で劇をして遊んでたわね」
……記憶の中の桜は、いつも緑色だ。
「春先は花見で輪の中心にいるけど、夏は放っておかれるから……映志ちゃんが遊んでくれて喜んでいたんじゃないかしら」
いわゆる桜の一張羅のピンク色で目の前に現れたって、気づくはずがない。
ただ彼女のおかげで、映志は子供の頃の夢を思い出し、色々な未来の可能性があることに気づくことができたのだった。
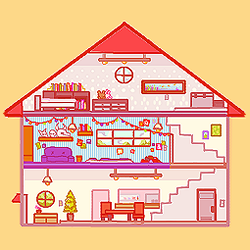
ゲームのシナリオや小説など、書くことを生業としています。音楽と旅行が好きです。