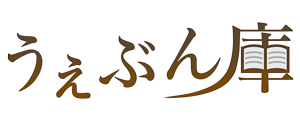じりじりと身を焦がす夏の暑さと、どうしようもない焦燥感で息が詰まる。
分厚い雨雲が晴れないまま盆休みに入ったが、長月(なつき)の高校生活最後の夏は、空模様以上に激しい嵐が巻き起こっていた。
「ただいま~」
「考ちゃん、おかえりなさい! 出版社から荷物が届いてたわよ」
「おぉ、この間言ってたやつかな……ありがとう」
隣の家から、楽しげに話す男女の声が聞こえてくる。
二階の部屋で読書していた長月は溜め息をつき、網戸にしていた窓を閉めに立ち上がった。
窓辺に近づくと、庭に出ていたらしい男女が、長月の存在に気づいたようだ。
「長月ちゃ~ん! 今、献本が届いたんだ。よかったら一冊受け取ってくれないかな」
隣に住む男――考時(こうじ)は長月の幼なじみで、数年前から仕事で小説を書いている。
長月は以前から彼の創作活動を応援しており、デビューした後も新作が出るたびに声をかけてくれるのを嬉しく思っていたが、今は複雑な感情にとらわれていた。
考時に寄り添う女から視線を逸らし、平常心を装って返事する。
「……大丈夫、新作なら予約してあるんだ。先生の本、すごく楽しみにしてたんだから」
「えっ!? そうなんだ、嬉しいなぁ……いつもありがとう!」
小さい頃から変わらない笑顔を見ると、心の靄が少しばかり薄くなったように感じたが――
「ふふっ、先生って呼ばれてるんだ。長月ちゃんって、考ちゃんのファン一号なのよね?」
「そうだよ。読書家で、いつも嬉しい感想を言ってくれるんだ。アドバイスも的確で、頼りにしてるんだよ」
「へぇ~……あたしはあまり本を読まないからなぁ。ごめんね?」
「ふふ、矢子さんはそのままでいいんだよ」
長月に向けられていた笑顔が、女の一言でいとも簡単に奪われてしまう。
考時に甘い声で矢子(やこ)と呼ばれる彼女は、彼がスランプで苦しんでいたときに気分転換で行った街で出会い、一週間前恋人として連れ帰ってきた女神だ。
勿論本物の女神ではないが、道を歩いていれば誰もが振り返るほどの美人であり、スランプに陥っていた考時を救ったため『創作』の女神と呼ばれているのだ。
憑き物が落ちてすっきりした顔の考時に矢子を紹介されたときのことを、長月は忘れないだろう。
左手にお土産を持ち、右手で女神と手を繋ぎ、考時は幸せそうに長月に言ったのだ。
「彼女に出会って、筆が進むようになったんだ。奇跡みたいだよ……! 長月ちゃん、気分転換の旅行を勧めてくれてありがとう!」
女神と出会うことになるなら旅行を勧めなければよかったなどと、長月は思いたくない。
彼女は、楽しそうに小説を書く考時が好きだった。
考時は長月が自分の『小説』を好きなことは知っているが、小説の何倍も彼のことが好きだということは知らないのだ。
ただ、小説の感想は伝えても、本人の前で直接恋心を露わにしたことは一度もなかった。
一度でも伝えていたら変わっていたのだろうか、と女神が現れてから毎日考えてしまう。
しかし考えれば考えるほど、ひびの入った恋心を細かく砕かれるような悲しさに襲われる。
長月の方がずっと長い間、考時を傍で見守りスランプ中も励ましていたのに、それでも彼は苦しんでいた。
矢子には、長月が持っていない力があるのだ。
長い献身など必要なく、一瞬の魅力で考時の心を奪っていった。
「……長月ちゃん、ぼうっとしてるけどどうしたの?」
「あっ、ごめん。暑くて疲れちゃった……のかも」
考時に声をかけられて、ハッと我に返る。
窓辺に立ったまま考え込んでいた長月の顔は、薄っすらと汗をかいていた。
遠目でも顔色が悪いことがわかるのか、声をかけた考時だけではなく矢子も心配そうな顔をしている。
「部屋の中でも熱中症になるから気をつけてね! こまめに水分補給したほうがいいわよ」
「そういえば、長月ちゃん前に本を読んでいると飲食を忘れちゃうって言ってたよね」
「う、うん……今も本を読んでたから、そのせいかもしれない……」
二人の心配そうな顔を見ると、恋心を砕かれ幾つもの穴があいた胸が痛んだ。
「……私、少し寝ようかな。またね、お兄ちゃん」
「うん、体調が悪いならゆっくり休んでね」
考時の言葉に頷き返し、窓を閉める。
ついでに日差しを遮るようにカーテンを閉めると、外から「お兄ちゃんとも呼ばれてるのね」と矢子の声が聞こえてきた。
考時が「幼なじみだからね」「久しぶりに呼んでもらえて嬉しいな」などと言っているのも聞こえて、長月は泣きそうな気持ちでいっぱいになる。
気が抜けて、懐かしい呼び方をしてしまった。
長月は思春期になった頃、考時に妹扱いされる自分を変えたくて呼び方を変えたのだ。
「いつか、考時さん……とか呼んでみたかったな」
呼び方ですら『考ちゃん』と呼ぶ矢子のほうが、考時と仲が良さそうなことに気づき苦笑する。
長月はふらふらとベッドに倒れ込み、読書途中の本を枕元に置いた。
何回も何回も読み込み、表紙やページの角が擦れてしまった本。
どちらかというと遅筆な考時が珍しく短時間で書き上げ、本人も気に入っていると言っていた作品だった。
当時、本を読んだ長月が感想を伝えると、考時は目を輝かせて言ったのだ――
「短い時間で勢いよく書き上げた作品は、きっとパワーがあるんだ」
「パワー?」
「うん。書き手である自分も納得できるほどの強いパワーがあったから、短時間で書けたんだろうし……ここまで熱を込められる作品に出会えたのは、奇跡かもしれない」
考時は、矢子に出会ったことも奇跡みたいだと言っていた。
ずっと傍にいた女の子よりも、一目惚れした女性の方が魅力的なのだ。
「それでも、私は時間をかけて愛したものに尽くしたいと……思っていたんだけどなぁ……」
夏が進むたび、隣の家から二人の声が聞こえるたび、長月の恋心は細かく砕かれ砂になるまですり潰されて――
秋の風が吹く頃には、きっと跡形も無くなっているだろう。
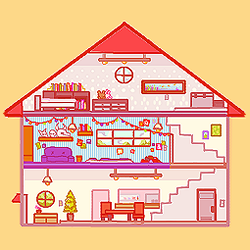
ゲームのシナリオや小説など、書くことを生業としています。音楽と旅行が好きです。