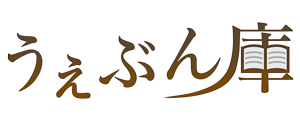とある小さな町で、便利屋を営む井浦の下に相談に訪れたのは、まだあどけなさが残る顔立ちの真面目そうな女性だった。
この春都会の大学を卒業して、地元で就職したという彼女――逢川幸(あいかわ さち)は、久しぶりに戻った実家で気味の悪い嫌がらせを受けていると言う。
――玄関ポーチに並べられた、ネズミと昆虫の死骸。
手のひらサイズの画面で見ると写真に何が映っているのか分かり辛く、井浦は画像を拡大したことを後悔した。思わず顔を顰めかけて、依頼主が目の前にいることを思い出す。取り繕うように咳払いしてから、テーブルの向かいで反応を待つ幸に携帯電話を返した。
「この状況が、ここ数日続いているんですか?」
井浦の確認に幸が小さく頷く。
「はい、この嫌がらせが始まったのは、ちょうど私が実家に帰って来てからなんです。親は、こんなことは初めてだと言っています。だから……その……」
「自分が問題なのではないか、と思ったんですね」
「……お察しの通りです。ただ私は、一人暮らしの間にこんな嫌がらせを受けたことは無いんです。一体私の何が原因なのかわからず……怖くて……」
俯く幸につられて視線を下に向けた井浦は、携帯電話を持った彼女の両手が、膝の上で震えていることに気付く。
「わかりました。俺が犯人を捕まえます――」
井浦は早急に事件を解決するため、手っ取り早く逢川家の近くで張り込むことにした。道路を挟んだ向かいに建つ一軒家に、以前井浦が依頼を解決した老夫婦が住んでいることも幸いして、近所の人々に怪しまれることなく逢川家を見守ることができたのだ。更に幸を幼い頃から知っていると言う老夫婦は、彼に決定的な情報を提供してくれることになった。
――その日の夜、幸が仕事から帰宅すると井浦が家の前で待っていた。近所で張り込むという話は事前に知らされていたため、幸も驚かない。
「逢川さん、お仕事お疲れさまです」
「いえ、井浦さんこそ……! あの……何か犯人の手がかりはありましたか?」
「手がかりどころじゃありませんよ、犯人を捕まえました」
「えぇっ!? ほ、本当ですか……!?」
辺りに響くほどの大きな声を出してしまい、幸は恥ずかしそうに口元を手で押さえた。顔の半分を手で隠しているものの、目は涙で潤みキラキラと輝いており、どこか肩の荷が下りたような安堵感が伝わってくる。
「ありがとうございます……! あの……誰が犯人だった……とか、何が原因だったかとか、聞いてもいいですか?」
「はい、ちょっと待ってくださいね。抱っこが難しいんです」
「抱っこ……?」
井浦は頷くと、逢川家と隣の家の間にある、大人が一人通れるくらいの隙間に近づいた。幸が不思議そうな顔で井浦を見つめていると、彼は隙間に両手を伸ばして何かを抱き上げる。
「あっ、いててっ! おいっ、暴れないでくれ……!」
隙間から現れたのは、大人の黒猫だった。井浦に抱かれるのが嫌なようで、どうにか逃げ出そうともがいている。
「い、いつからそこにいたんでしょう……気づかなかったです」
「隠れていたみたいだから、それは仕方ないです。色も黒くて、この時間になったら余計見え辛いでしょう。こいつが、逢川さんにネズミやら昆虫やらをプレゼントしていたんですよ」
「ぷ、プレゼント!?」
「はい……っ、その、また逢川さんを驚かしてしまうかと思って先に片付けてしまったんですけど、今日も置かれていました。片付けたりしたから、俺のこと嫌がってるのかな?」
井浦は黒猫を落ち着かせることを諦めて、地面に下ろした。黒猫はやれやれだと言わんばかりに「にゃっ」と井浦を威嚇すると、再び家と家の隙間に戻ってしまう。しかし一度そこに<いる>ことを意識すると、暗闇から黄色の目が2つ、こちらを窺っていることが分かる。
「あの子、どうして私にプレゼントをくれるんでしょう?」
「逢川さんにお礼をしているんじゃないか、と俺は思っています」
「お礼ですか? 一体何の……――あっ」
不意に何かを思い出した様子の幸が、暗闇を見つめる。そして恐る恐る、両手を広げて見せて……「もしかして、ヨルちゃん?」
幸の震える声に応えるように、黒猫が飛び出してくる。井浦に抱き上げられて暴れていたのが嘘のように、まるでそこが自分の居場所なのだと言わんばかりにすっぽりと、幸の腕の中に収まったのだった。
「私のこと、覚えていてくれてありがとう……ヨルちゃん」
――なぜヨルが、幸にプレゼントを贈り始めたか。
それは幸が小学生の頃、近所の悪ガキどもの罠にかかった野良猫を、助けたことがきっかけだった。最初は人間を警戒していた野良猫も、幸を味方だと認識するとすぐに懐き、毎日家まで会いに来るようになった。野良猫にヨルと名付けて可愛がっていたものの、小学生だった幸は大きくなるにつれて、学校の部活やバイトで帰る時間が遅くなり、大学に合格してからは家を出てしまう。実は幸が都会で大学生活を送っている間も、ヨルは何度も逢川家に訪れて家の前をウロウロしていたことを向かいに住む老夫婦は知っており、その情報を井浦に教えてくれたのだ。ヨルは、また幸に出会えたことへのお礼をしていたのだろう。
そして後日、井浦の元に幸から手紙が届いた。
ヨルを家族として迎え入れたという嬉しそうな知らせと、1枚の写真が添えられている。
玄関ポーチに並べられた綺麗な花と、その横で幸せそうな顔をして寝転ぶヨルの写真だ。
健気な野良猫の一途な想いが実ったのだと思うと、井浦の頬は自然と緩んでいた。
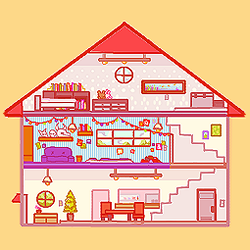
ゲームのシナリオや小説など、書くことを生業としています。音楽と旅行が好きです。