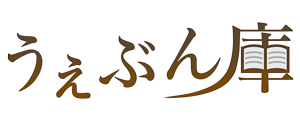「なんて言ったらいいのかわからないけれど……」
箕輪先生は、目の前の私を見つめた。
千葉県の郊外にある、悪名高い某医学系予備校の受付嬢として勤め始めて三ヶ月。私は早々にここを去ることになった。理事長のバカ息子とケンカしたとか、その息子の弟と結婚させられそうになったとか、予備校自体ほとんどつぶれそうで給料が支払われなかったとか、あえて探さなくても理由はいくらでもあった。
短い間に随分いろいろなことがあったなぁと思い返した。正直、随分濃い時間だった。何人かの先生と恋をし、十代の生徒に告白され、その後日談を含めて日本の法律を考えると人前で話せるようなことはあまりない。
たくさんの人と仲良くなった三ヶ月。私が去るとき皆が口々に、「寂しくなるよ」と言ってくれた。生徒の数人からは手紙をもらい、「ショックです」と泣かれた。
箕輪先生とは、あまり話したことがなかった。若くて背の高い、理系の静かな先生で、飲み会でもほとんど口をきかなかった。辞める日が来ても、私は勤めて明るく振舞っていたので、最後の挨拶回りもあっけらかんとしたものだった。仲の良い同僚たちとは連絡先を交換していたし、すぐにまた会えると思っていたから挨拶なんて表面的なものだと思っていた。
だから、箕輪先生と向かい合ったとき、その静かな一瞬に戸惑った。
「箕輪先生、お世話になりました!」
ほかの人たちにしたのと同じように明るく言うと、先生は黙って俯いた。生徒たちがいなくなったガランとした教室で、私たちは二人きりで向かい合っていた。箕輪先生は、冒頭の言葉を言うと、それきり黙って私を見つめた。私はどうしたらいいかわからなくて、思わず俯いた。口を開きかけたけど、私もやはり言葉は見つからなかった。しばらくの沈黙のあと彼はそっと片手を差し出すと、「……元気でね」と言って静かに微笑んだ。
あれから何年もの月日がたち、ほかの人のことはみんな忘れてしまったけれど、なぜか彼のことをふと思い出すことがある。
箕輪先生のさよならは、ほかの人のさよならと違っていた。もう二度と会えないときの「さよなら」だ。彼だけが、人生のなかのほんのいっとき、私ともう二度と会えないということに想いを馳せてくれたのだ。「またすぐに会えるもんね?」と、軽口をたたきあい、表面的に仲が良かった同僚たちから口癖のように繰り返された「寂しい」よりも、何も言わなかった彼の想いの方がどれだけ重くて大事か、私は考えた。口先だけのさみしさもさよならも要らない。私が欲しいのは本物の方だ。あのとき、わかったのだ。言葉にならない時間のなかに、いつでも大切な気持ちがある。
あれから十年の月日が流れた。
「お待たせしました。……あれ、ひとみさん?」
お気に入りの喫茶店でひとりお茶していると、アールグレイを運んできたウェイトレスが、突然私の名を呼んだ。
「そうですけど、あなたは、誰……でしたっけ?」
目の前の女の子の顔、確かにどこかで見た気はするけれど、思い出せない。
「私、予備校の生徒です。ひとみさんにバンソーコもらったりしたの、覚えてないですか?」
あぁ! 思い出した。備品の絆創膏が切れていて、私がそのとき持っていたキャラクターの絵柄の絆創膏をあげたのだった。あの時は制服姿だったが、化粧をしてきれいになっていたのでわからなかった。もうすぐ仕事が終わるので、少し話していってもいいかと彼女は言った。断る理由もないのでOKした。
彼女は私が辞めたあとの色々な話をしてくれた。予備校は、結局あれから3年後につぶれたらしい。
「そういえばね、ひとみさん。箕輪先生って覚えてる?」
「もちろん覚えてるよ」
「先生ね、亡くなったんだよ。ひとみさんがやめた半年後くらいに」
私は言葉を失った。
「病気だったみたい。私たちも亡くなるまで誰も知らなかった。
先生、きっとひとみさんのこと、好きだったよ」
「……どうしてそう思うの?」
「箕輪先生、ひとみさんがやめたあと、ずっと元気なかったから」
彼女と別れたあと、私はひとりトボトボと歩いた。
私はなんにもわかっていなかった。あのときの先生のさよならは、――。
どこを歩いてきたか覚えていないけど、いつの間にか家に着いていた。押し入れを開けると、埃かぶった箱が目についた。予備校を辞めた時に「先生たちみんなから」と、もらったカップだ。なんの飾り気もない耐熱のカップで、正直あまり趣味じゃないから一度も使わずにしまっていたのだけど、初めて出してみた。
洗って、箕輪先生がよく飲んでいた紅茶を入れてみる。……ホットのアールグレイ。
熱いからだけではなく、喉がギュッとなる気がしてなんだかうまく飲めない。
ふと気が付くと、カップの側面に文字が浮かび上がっている。
「Thank You」
お茶のなかにポタポタと涙が落ちた。どうしていつも、後になって気づくのだろう。
伝えられたことがすべてじゃない。伝えられなかった想いは、まるで渡せなかったプレゼントみたいにいつまでも、心のなかに残るんだ。

1979年生まれ。ショート&ショート、エッセイ、児童文学を中心に創作活動を行う。