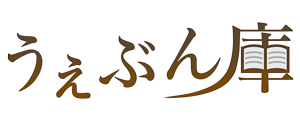田舎にある人口800人ほどの小さな町、桜尾町。
この町唯一の中学校、桜尾中学校では大きなイベントが行われる予定だ。
「おーい、そっちは準備できたか?」
「バッチリっす!」
「ちょっとこっちの飾り付け手伝って~!」
全校生徒12人のうち11人は教室の飾り付けをしていた。赤、青、黄、緑、紫。様々な色で教室は彩られ始めていた。時刻は午前6時。始業にしては少し早い。
「朔はいつも7時には学校に来てるから、急いで!」
その中で中心にいるのは三年生、和原 美也子だ。美也子はテキパキと下級生達へと指示を出しながらしかし自分の手は止めず、細い短冊状の折り紙を糊で止めて輪飾りを作っていた。
「朔先輩のためだもん、絶対に成功させましょうね!」
「ええ、もちろん」
美也子の後輩である佐々木 和の手も借りて机一杯に次々と輪飾りを量産していた。
と、いうのも今日は山内 朔の最後の登校日。朔はこの中学校に通う美也子以外のただ一人の三年生だ。そして美也子の想い人でもある。
「朔先輩が転校だなんて、寂しくなりますねぇ」
「五月蠅い人が居なくなって勉強に集中できるわ」
「そんなこと言って先輩、朔先輩のこと大好きなくせに」
「そ、そんなことないわよ!」
「告白しちゃえば良かったじゃないですか」
「…………和、口じゃなくて手を動かしなさい」
はーい、と少しだけニヤニヤする和を横目で睨みながら美也子は小さくため息をつき、お見送りパーティーの飾りを再び作り始めた。
普通ならば数日前から準備を始めているものだが、季節外れの大雨で学校が休校となり、あえなく今日の始業前にパーティーの準備をしていたのだった。
「朔先輩、なんて言いますかね!」
「さぁ、どうかしら。朔のことだから案外すぐに忘れてしまうかもしれないわ」
和はニコニコと微笑みながら美也子へとたずねる。美也子は特に普段の表情のままその答を返した。
しかし内心は違う。
笑ってほしい。喜んでほしい。ずっと思い出に残っててほしい。私達のことを忘れないでほしい。
そんな思いがぐるぐると美也子の頭の中を巡っていた。
***
時刻は9時を過ぎた。一向に朔が来る気配はない。
「あいつ、一体なにやってるのかしら……」
朔が普段通う道には今朝謎解きを美也子が置いていた。しかし何時間もかかるほど難しいものではない。
「朔先輩、遅いですねぇ」
和が余った折り紙で鶴を作る。既に飾りつけは終えてあとは主役を待つだけだ。しかし来ない。
「朔にメッセージ送ってるんだけど、全く返事が来ないのよ」
美也子はスマートフォンのメッセージアプリを開く。しかし朔からの連絡は0件だ。こちらから送ったメッセージだけがずっと連なっていた。既読はつかない。寝ているのかしら、と呟いて端末をポケットへと仕舞う、と同時に。
「おーい、和原!」
「先生」
教室に先生が入ってきた。片手には携帯電話が握られている。
「山内の親御さんに連絡したが、もう3時間ほど前に家を出ているって」
「……え?」
朔の家から学校までそう遠くない距離にある。遅くても1時間で着くはずなのだ。
それが2時間以上もかかるなんて、普通ではありえなかった。
「わ、私。探してきます!」
「美也子先輩!?」
美也子はたまらず教室を飛び出した。後ろで和が美也子を止めるのも振り払い上履きのまま外へ飛び出した。
随分と道路は濡れていた。あちこちに水たまりもあったが、美也子はそれに気を付ける暇もない。バシャバシャと水たまりを踏めば、上履きの中はすぐにじっとりと湿る。
額に大粒の汗をかくのも惜しく美也子は足を動かした。
「朔、どこにいるのよっ」
むやみやたらに探したところで小さな町とはいえ、会える確率は低い。
ふと美也子が横を見ればそこには川があった。昨日の雨で随分と水かさが高くなっていて、川の勢いも普段に比べてとても速い。
「もしかして……!?」
一つ、嫌な予感が美也子の頭に思い浮かぶ。思い当たる節はあった。朔が普段からよくいた場所。川の河川敷だ。
美也子は必死に走った。
別れがこんな風になるなんて嫌だった。最後に見た朔が悲しい顔なのも嫌だった。
何より、もう朔と会えないなんて嫌だった。
一瞬にも、永遠にも感じた時間が過ぎて、美也子は目的の場所へと辿り着いた。増水した川が普段朔の座る草地を覆っていた。
「さく、さく……朔!」
辺りを見回して、人影を探す。川の中。対岸。草木の中。辺りを満遍なく探そうとして、しかしすぐに朔は見つかった。
「あれ、美也子。どうしたの?」
ドロドロになった制服と、抱きかかえていたのは猫だ。
「…………はぁ?」
「あ、この猫。可愛いでしょ? さっき川に流されそうだったところを拾ったんだけど痛い!」
朔は猫を撫でようとして、その爪で手を引っかかれる。しかしニコニコと笑顔を浮かべる彼を見て美也子は
「なんなのぉ……あんたぁ……」
思わずその場にへたり込んだ。
「あ、携帯もない!」
「……馬鹿。川に落としたんじゃないの?」
なんだか張りつめた気持ちが一気に緩んでしまったようだった。美也子はため息をついて「……良かった」と呟いた。
***
美也子が学校に連絡を入れて、2人はゆっくりと、話しながら学校へと向かった。
どちらかと言えば美也子が朔の今日あった出来事を問い質す形ではあったが、笑いながら、そして今までの学校生活を懐かしみながら、最後の登校を終えた。
「ほら、入りなさいよ」
「え?」
教室の前に2人はいた。キョトンとした表情を浮かべて朔が扉に手をかけた。ガラリ、と音を立てて扉が開けば、辺りからクラッカーの音が鳴り響き、紙吹雪が散らばった。
「朔先輩、今までありがとうございました!」
美也子が見たのは、飛び切り嬉しそうに、はちきれんばかりの笑顔の朔だった。
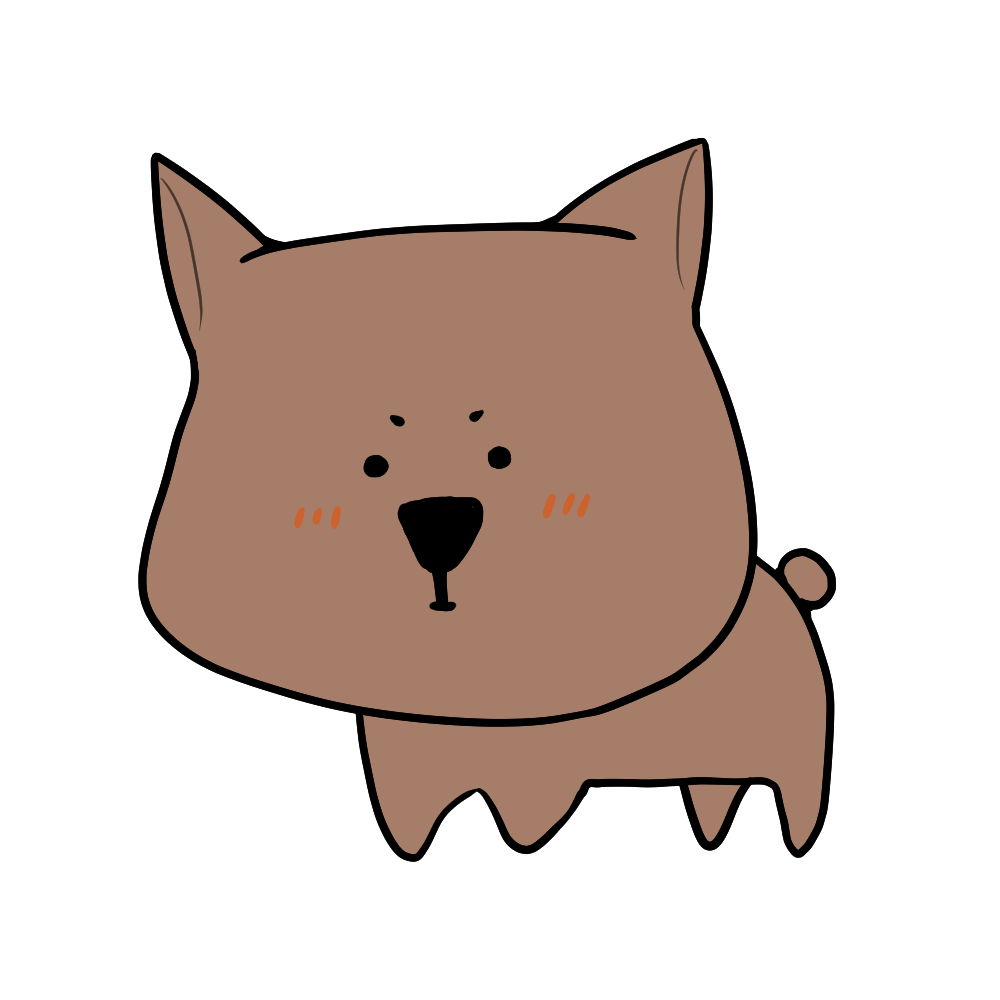
こんにちは。医学を専攻する物書きの端くれ、荒木るんどです。ゆくゆくは全米を超えて全世界が涙する小説を書くのが今の目標です。