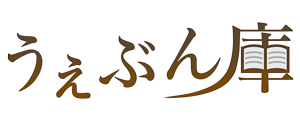僕は君のことが嫌いだった。眩しい笑顔、君はなぜこの閉鎖的な空間の中でもそんなに明るくいられるのか分からなかった。ただ、一つ分かっているのは君がいてくれたおかげで僕は変わり映えのない毎日から抜け出すことができたよ。ありがとう。
僕がこの病室に入院してから、1ヶ月が経った。
僕は生まれつき肺が弱く、今回も肺に関する手術をしないと危険な状態だった。
要は、肺を提供してくれる人を待っていた。
そんな僕が最近、不快に思うことがある。
それは……
「おはようございます!」
来たよ……。あの女。何でもボランティアとしてこの病院で働いている人らしい。
だけど、僕にとってはとても不快に思わせてくれる人。
元気いっぱいのあの笑顔、毎日が楽しいって感じのあの雰囲気。
本当に見ていて、イライラしかしなかった。
あまり動くことができない人、感染症などにかからないようにこの病棟から出てはいけない人のために看護師に代わって買い出しに行ってくれる。
だから、朝の挨拶がてら病室を周りに来る。
「おはようございます! 何か買い出しとかありますか?」
「いえ、特にないので大丈夫です」
僕は毎日やってくる彼女にぶっきらぼうに答える。
「了解しました。何かあったら言ってくださいね」
こんなやりとりが1ヶ月。取り敢えず、あまり僕には構わないで欲しかった。
この頃の僕は、いつ来るのかも分からない知らせを待つことに嫌気がさしていた。
そんなある日の夕方、僕がデイルームに出て外の景色を見ようとしていた時に彼女が座っていた。
最悪な鉢合わせ……。
僕はそう思って、自分の病室に引き返そうと思った時…
「こんにちは!」
彼女が気付いてしまい、声をかけられた。
「どうも……」
僕は、そのまま引き返すことができる雰囲気ではなくなり、仕方なく窓に近付いて景色を見ることにした。
この景色をあと何回、ここから見るのだろうか…そう考えていた時に。
「すぐに良くなりますよ」
彼女が言葉を発した。
「どういう意味?」
「あなた今、あと何回この景色をここから見続けるのかって顔をしていたからもうすぐ良くなりますよって返答をしました」
そう言ってニコニコと笑顔を見せる彼女。
もうさすがに我慢の限界だった。
「そんな簡単に言うのはやめて欲しい。君には分からないでしょ?
どれだけ待っていても良い知らせが届かない人の気持ちなんて。
健康な君に何が分かるの?」
少しの間、沈黙が続いた。
言いたかったことが言えて、自分の中ではすっきりし、その場を立ち去ろうとした時だった。
「私にはね、大切な友人がいるの。その友人はね、心臓の移植を待っているの。
彼女はもう半年近く待っているわ。最初は君みたいに嘆いていたの。
でも、それをやめて笑顔で過ごすことを決めた。毎日の人生を悔いが残らないように生きようって決めたの。そうしないと、万が一のことがあった時に悔いが残った人生を思い出すのは嫌だって思ったみたい。あなたも、自分の人生を嘆く前に少しでも良いから楽しく過ごそうって考えを持つことも悪くないと思うよ」
僕は、何も言えずそのまま彼女に背中を向けたまま立ち去った。
思い返してみれば、入院した当初から嘆いてばかりで楽しいことなんて一つもなかった。
そんな人生で僕は本当に良いのだろうか……。
彼女の言葉からそれを考えさせられた。
翌日から、彼女が病室にやってきていつもみたいな口調で話し掛けてきても不快に思わなくなった。
寧ろ、僕の方から声をかけることもあり、彼女との会話を楽しんでいた。
こんな毎日が続き、少しずつだがこの日々が楽しいと感じるようになった。
「あなた、最近笑顔が増えたよね! 凄く良いと思うよ!」
彼女のその言葉で、自分が前みたいに卑屈な感じではなく、楽しく日々を過ごそうとしていることがわかった。
だが、その会話を最後に彼女は翌日から姿を見せなくなった。
看護師に聞いても
「なんか風邪を拗らせたらしくて、しばらくは行けないって。
だから、君にしばらくの間はお願いするって言ってたよ」
その言葉を聞き、僕は彼女が戻ってくるまでの間毎日必死にやってみせた。
そんな日々が3ヶ月も続いたある日のこと。
医者がいつもの回診時間外で、僕の病室にやってきた。
「実は、ドナーが見つかったんだ。君の体調が大丈夫かもう一度チェックをして大丈夫と判断をされたらすぐに手術を開始するよ」
その日に、検査を全て受け、大丈夫との判断が下った。
そして手術日程もすぐに決まった。
僕は、自分がしばらく動けなくなるため、彼女に何としてもそのことを伝えたかったが、彼女との連絡手段がなく、看護師もプライバシーの保護などの名目で一切教えてくれなかった。
手術当日。
僕は、麻酔がかかると夢を見た。
その夢には彼女が出てきた。
彼女に話したいことがいっぱいあるのに、声が出ない、体が動かない。
だけど、彼女は微笑んで“おめでとう、これからは自分の人生を楽しんで”と言って立ち去った。
彼女を追いかけようとしたところで、麻酔が切れ、目が覚めた。
その後の術後の経過も良く、退院となった。
退院の日。
僕と彼女と仲良くしてくれていた看護師が1通の手紙を持ってきた。
それは彼女が僕に宛てた手紙だった。
【この手紙があなたのもとに渡るようにお願いしました。前に話した友だちの事を覚えているかな。あれは、私のことだったの。私の心臓はもう持たないみたい。私は、この数週間あなたと過ごせた日々が本当にかけがえのないものになったそう伝えたかったの。私は元々、ドナー登録をしていたから……もしも私に何かあった時はあなたの役に立てたら嬉しいなって……なんてね! お互い病気が早く治ると良いね】
そう締め括られていた。
僕は顔を上げて聞こうとしたら、看護師が首を横に振った。
僕はそれだけで彼女の状況を察した。
もしかしたらあの夢は、彼女が最期に、僕にそれを伝えるために来てくれたのではないかと思った。
僕は彼女が教えてくれた日々の過ごし方を噛み締めて、病院を後にした。

初めまして。小学生の頃から物語を書くことが好きで、高校生では携帯小説を書いていました。今は、小説やシナリオを書いています。主に得意なのは、恋愛小説や友情モノの小説です。ゆくゆくは、他のジャンルも書いていけたらと思っています。