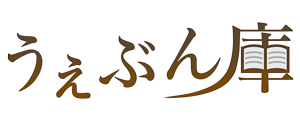朝起きたら必ず彼に挨拶をする。サラサラとした手触りの良さそうな黒髪。儚げな白い肌。図書室の片隅が似合いそうな、控えめな顔立ち。壁際に佇む彼に触れることはできないけれど、わたしはいつも彼の存在に助けられている。
「こよみ、早くご飯食べちゃいなさい」
階下から母親の呼ぶ声が聞こえる。声の調子から忙しなく家事をしている様子が目に浮かんだ。
あーあ。現実の世界はちっともキラキラしていない。ずっと彼を見つめていたい。でも、そんなことをしていたら学校に遅刻してしまう。
「またあとでね」
声をかけても返事はない。彼はポスターなのだ。
わたしの部屋に張られているポスターの人物。それは今最も勢いのある人気声優さんだった。子供の頃からアニメを見るのは人並みに好きだった。本格的にハマり始めたのは『幽霊部長とヴァンパイア』というアニメ作品に出会ってからだ。図書室の地縛霊である幽霊がヴァンパイアと出会い、ひょんなことから図書委員の部長を任されることになるという学園ファンタジーなのだが、その主人公の声を担当していたのが彼だった。
幽霊の儚さとアンニュイさを含んだ声色で若い女性を中心に爆発的に人気となり、わたしも例外なく彼の虜になってしまった。
「昨日の『幽霊部長』観た?」
教室に入ると、クラスで一番仲の良いキク田がおはようも言わずに声をかけてきた。キク田は本当は「菊田」だ。漢字を書くのが面倒くさくてみんな彼女の名前を書くときはカタカナで書いているのだった。
「まだ観てない。録画してある。ネタバレ厳禁ね」
「わかってるって。ネタバレは死刑だもんな」
キク田は言われるまでもないという顔をして頷く。
「こよみ氏、バイト忙しそうだな」
「うん。推しに貢ぐためね」
「ヨッ! オタクの鏡!」
わたし達オタクは推しである大好きな声優さんのグッズやDVD、ドラマCDを買うために努力を惜しまない。放課後はバイトを入れて、土日もフルで働いている。年に数回ある声優さんのライブやイベントに行くため、チケット争奪戦への参加も欠かさない。これも自分の幸福のため。推しのためだ。
「ところでこよみ氏、水を差すようで悪いんだが進路希望調査は出したでござるか」
「ヒィッ……! 出してないでござる……」
「締め切りは明日でござるよ」
哀れな子を見るような目でこちらを見つめる。
「ちなみに拙者はもう出したでござる」
ああ、なんてこった。同じ穴のむじなだと思っていたのに。毎日アニメの話ばかりしていたから、進路のことなんて全然考えてないと思っていた。
でも、そうか。わたし達ももう高校三年生。アニメ好きなだけじゃダメなんだな……。
「どうりでお母さんが塾に行けって言うわけだ」
ガクッ。首が自然と傾く。
「キク田は進路どうするでござるか。参考までに聞かせてほしいです」
もはや侍の口調を真似る元気もない。素の声に戻ったわたしに合わせて、キク田も素の声に戻って言った。
「わたし、声優になりたいんだ」
「えっ……、そうなんだ……」
彼女の、かつて見たこともないほど真剣な眼差し。わたしは目を反らせなくなる。
「そうなんだ……」
チャイムが鳴った。慌てて席に戻る。先生が入ってきてはつらつとした声で出席を取るも、わたしの気分はさっきまでキク田と話していた場所に置いてけぼりだった。
「ねぇ、どうして声優になろうと思ったの?」
やっぱりアニメが好きだから? とわたしは尋ねる。昼休み中の教室はガヤガヤと騒がしく、わたし達の会話を周りから聞こえないようにしてくれる。
「わたしね、中学の頃いじめられていた時期があって、不登校にはならなかったけど学校行くのがしんどい時があったのね。死んじゃいたいと思った時もあった。そんな時、元気付けてくれたのがアニメだったの。現実がどんなにしんどくってもアニメを観ると元気が出る。アニメを観ている間は現実の嫌なこと忘れられるんだ」
だから声優さんになりたいって思ったの。そう言って、キク田は照れ臭そうに笑った。
そうだよね。アニメ観ている間は嫌なこと忘れられるよね。わたしもアニメが大好きだ。でも、わたしには声優さんになりたいって言えるほどの自信も度胸もなかった。
キク田との会話と、自分の進路と、大好きな推しとがぐるぐる頭の中を回る。そんなんだから授業にも集中できず、いつの間にか学校は終わり、わたしは家に帰っていた。
「ああ、そうか。進路のこと考えなきゃと思って、提出日の前日は休みにしていたんだ」
アルバイトに行こうとして手帳を確認し、過去の自分の考えを思い出す。
「ギリギリにならないとやらない性格なんだよな」
進路希望調査を机の上に放置したまま、ゲームをやりだす始末。我ながら情けない。あーあ、と溜息を吐くと推しと目が合う。壁際の彼はいつもと同じポーズでいつもと同じ眼差し。相変わらずかっこいい……
「じゃなくって!」
あー、もう! と立ち上がり、わたしはプリントに殴り書きをした。第一希望、S大学。彼の出身校だ。正直、どんな学科があるのかも知らない。自分がどんな勉強をしたいのかもわからない。だけど、進路は決めなきゃ行けない。
「不純な動機だっていいじゃん」
だって、好きなんだもん。彼のことが。
壁際に目を向けると、夕日を受けた彼の頬が微かに赤く染まっていた。

ファンタジー、恋愛、児童向け小説を書いています。電子書籍「出会った王子と船の旅」、「イチ・ナナ・キュー」。恋愛小説投稿サイト・プリ小説にて公式作家として「宝ひかるは石の国」、「イケメン過剰摂取につき死亡しました!」好評連載中。アイコンはkaoliniteさん(twitter@okayuiatsui)から。