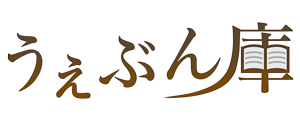残暑が厳しく、寝苦しい夜だった。夏が終わろうとしていた。
カレンダーを見る。今日は八月三十一日。
「明日から九月、か」
そこで、ふと私は十五年前の今日を思い出す。夏休み最終日の夜をだ。
十五年前。具体的な年齢を述べるのは差し控えるけれど、あの時の私は小学生で、それはそれは楽しい毎日を送っていたものだ。
鬼ごっこに缶蹴り、お手玉にかくれんぼ……それに男の子たちに混じってのゲーム大会。
「はあ……」
でも、いまの私には何もない。
会社に勤め、毎日やりたくもない仕事を機械的にこなし、希望も未来もない日々。
いっそあのころに戻れたら……。いや、そんなことを考えていても仕方がない。
目をつむる。
いまはただ泥のように眠って、明日からの仕事に備えるだけだ。
おやすみ、私。
さようなら、夏休み。
***
「おかしいな」
翌日。私はスマートフォンの画面を眺めながらそう言った。
今日は九月一日、のはず。
しかし、スマートフォンの指し示す今日の日付は八月三十二日になっていた。
「壊れちゃったかなあ……」
しかし、ありもしない日付が表示されるなんて、こんな壊れ方は聞いたことがない。
うるう年だからというわけでもない。それは去年に過ぎてしまった。
わけがわからない。
さいわい時間の表示は正確なようで、それだけが救いだ。
混乱する頭を無理やり落ち着かせる。九月が来ても来なくとも、会社には行かなければならない。
帰りに、修理に持っていくことにしよう。
修理代、高くつかないといいな。
そう思いながら、私は家をでた。
***
会社に行くと、門前払いを食らった。
顔も知らない社員から告げられたのは、「部外者は立ち入りできません」という一言のみ。
しかしそんなわけがない。
私は社員証を見せたりして抵抗したけれど、それも意味をなさなかった。
挙句の果てに警察を呼ばれそうになって、私はあわててその場を逃げ出した。
いったいぜんたい、何が起きているのだろう。
とつぜん予定を奪われた私は、ひとまず近くの公園に足を運ぶことにした。
小学生のころの夏休み、よく友達と遊んだ公園へと。
***
ベンチに腰を下ろす。
「はあ……」
これから、どうしよう。
いっそ、向こうから連絡が来るまでサボってやろうか。
それで、連絡が来たらこう言ってやる。「よく確認もせずに追い出したのはそっちでしょう?」と。
「ふふ……」
そんな想像をしていると、なんだか気分が少しだけ軽くなってくる。まるで夏休みが延長したかのような気分だ。
子供たちの声が聞こえてきたのはそんな時だった。
わいわいと、子供特有の甲高い声が公園に響く。
子供たちは集団で、グループの内訳はこうだ。髪の長いポニーテールの女の子、眉毛の上で前髪を切りそろえたおかっぱの女の子、ぼろぼろのジーンズを履いた無邪気そうな男の子、そして……。
あれ?
そして、ようやくのことで私は気づく。
あれは……私だ。
肩下にそろえられたキレイな黒髪。
邪気を知らない笑顔。
一人が合図し、いっせいに駆け出す。鬼ごっこを始めるようだ。
鬼役は私だった。
いーち、にーい、さーん……と子供の私は数を数える。
ご! とカウントし終えて、私は友達たちを追いかけ始めた。
子供の私は、一人の男の子を必死に追いかける。
しかし、いくら子供といえど、男の子の脚力に女の子の私が敵うはずもない。
それでも私はあきらめなかった。
あきらめずに、がむしゃらに男の子を追いかけ続けた。
そういえば……と、私は今さらながらに思い出す。
あの男の子は、私の初恋の人だ。
思わず笑みがこぼれる。結局叶わなかった恋だけれど、それでもほほえましく思えた。
子供の私が、ぜえぜえと息を荒くする。
ずいぶん長いことその男の子と追い駆けっこを続けていたのだ。仕方がない。
すると男の子はわざと歩調をゆるめて、私にわざと鬼役をバトンタッチさせた。
そうそう。こんな優しいところに惹かれたんだよなあ。
疲れている私を、いつだって気遣ってくれる。
「お姉ちゃん」
不意に声がした。顔をあげると、そこにいたのはその男の子だった。
「へ?」
とつぜんのことで、私はおかしな声をあげてしまう。
「どうしたの?」と男の子が私に訊く。
「どうしたの、って?」私は訊き返した。
「なんだか疲れてるみたいに見えたから」
「……っ」
私は思わず言葉を詰まらせた。
そっか、君にはお見通しなのか。
「うん、そうだね。私、ちょっと疲れてたかもしれない」
私は続ける。「でも、もう大丈夫」
「そっか」
男の子はほほえむ。「なら、よかった」
***
目覚めるとそこはベッドの上だ。
あわてて確認すると、スマートフォンは九月一日を示している。
今のは、何だったのだろうか。
夏のカゲロウが見せた一時の夢……なんてロマンチックな表現で事を片付けるにしては、今の出来事はあまりにも現実味を帯びすぎていた。
「まあ、でも、いいか」
夢か現実か、それはわからない。
それでもこの胸のほのかな暖かさは本物だと、それだけは断定できた。
「よし、今日もがんばるぞ」
私はひとりごちる。
出社までもう時間がない。私はあわてて準備を終えると、家を飛びだした。
駅までの道をひたすらに駆ける。
しかし日ごろ運動不足なためだろうか、すぐに息があがってしまった。
立ち止まり、ぜえぜえと息を吐きながら呼吸を整える。
情けない。一度はあたたまった気持ちが、ふたたび冷めていくのを感じる。
もう、このまま休んでしまおうか。そんな思いが眼前をすうっと横切った。
そんな時だった。
「大丈夫ですか?」
ふと、声がした。なんというか、懐かしい声だ。
優しくて、いつだって私を助けてくれて、いつだって私を気遣ってくれたあの声。
ああ。
君は、いつも私に優しくしてくれるんだね。今も昔も――もしかすると、これからも。
私はその声に答えようと、ゆっくりと、それでもたしかに顔をあげた。
さようなら、夏休み。
おはよう、私。

文字を書いて生きています。