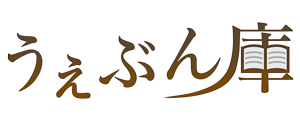ずっと大好きだった子に、俺は告白をされた。
「あの、さ」
マフラーをぐるぐるに巻き、顔を埋める彼女はその場で足を止めた。
俺は一、二歩進んだところで、彼女の声に足を止め、振り返った。
「ん?どうした?」
「……。」
視線を合わせない彼女に、俺はもう一度声をかける。
「杏、体調でも悪いのか?」
「……違う」
首を振りながら答える彼女は、そのまま言葉を紡いだ。
「私……康太のことがずっと、好きだった」
予想もしなかった言葉に、俺の脳内は白フラッシュをくらったかのように、何も考えられなくなる。
「……あのね、「ちょっと待て、杏」
「――え?」
俺は杏の言葉を途中で無理やり止めた。
だって、信じられなかったんだ。
ずっと隣にいた女の子が。
昨日まで普通に俺の家で一緒にゲームをしてた杏が。
俺の事を好きだなんて。
「冗談はよせって。何の罰ゲーム?」
「ちがっ……」
「はいはい。嘘はエイプリールフールにつくんだな。そんな冗談に俺は騙されないからな」
笑い飛ばした俺をみて、杏は何を思ったのだろうか。
「――っ、」
俺は子供だから気が付かなかったんだ。
マフラーからのぞく頬が赤いのは、寒さのせいだって。
杏が微かに震えてたのは寒いからだって。
目に溜まる涙にすら、気が付けない俺が、杏の本当の気持ちになんて気が付けるわけもなくて。
「バイバイ……っ」
それが、彼女との最後の会話になるなんて――。
「……杏……?」
思いもしなかったんだ。
***
「おーい、康太」
「久しぶり。春休みぶりだな」
「おう。ついに大学生だな。うっひょー!!さすが都会の大学。可愛い子が沢山いるぜ!」
「あんま浮かれんなよ」
「はいはい。そういうのは彼女の一人作ってから言いましょうねー!」
「うるせー」
優しい風が、頬を撫でてた。地面に落ちてた桜の花弁が、徒競走をするかのように地面を走り出す。揺れる梢から落下するその花たちは、俺の心のように不安定に揺れ踊る。
「入学式行こうぜ」
友人の言葉に軽く頷いて、足を一歩、また一歩と大きな会場へと向けていく。
杏がいなくなってから、5度目の春を迎えた。
あの告白の後、春休みに入ってしまった俺たちは会うことはなかった。そして新学期、杏は引っ越したと担任に告げられた。親父さんの急な転勤だったそうだ。そのため誰も杏が転校することを知らなかった。
(あ~…だるいな。入学式、早く終わんねーかな)
さすが都内の有名私立大学。何人いんだよってぐらい、人がいる。
『新入生代表の言葉』
「なげーなー」
隣に座る友人も退屈そうだ。
長い入学式に嫌気がさし、あくびをしそうになったその時だった。
『―――海江田、杏』
「はいっ」
眠気が一気に吹き飛んだ。
珍しい苗字、呼ばれた名前に、透き通った声を、俺は知っている。
(……杏……?)
いや、まさかそんな偶然あるわけない。
そう思って、ジッと新入生代表の言葉を読み上げる彼女に視線を送る。
しかし2階席に座る俺の場所からでは遠く、壇上に上がった彼女の姿をしっかりと確認することはできなかった。
そこからの記憶はほとんどない。
頭の中は先ほど呼ばれた彼女の名前で一杯だった。
式が終わったと同時に、俺は走り出す。
何も考えずに、ただただ階段を駆け下り、1階席に座っていた彼女が出てくるであろう入り口の近くに立つ。
ゾロゾロと川の流れのように人が出てくる中に彼女の姿がないか探す。
先ほど呼ばれた名前が、本当に杏なのか、俺の心臓はきっとこの大学の合格発表の時より波打っている。
しばらく待ったが、彼女らしき人物を見つけることはできなかった。
(やっぱり違う人だったんだ)
いるわけない。そう自分に言い聞かせて、その場を去ろうとした時だった。
「――康太……?」
呼ばれた名前に振り替える。
「……杏?」
「やっぱり、康太だ」
そう言って笑う彼女のえくぼに、俺はなぜかホッとしたんだ。
背丈も俺と同じぐらいだったのに、いつの間にか俺のほうが大きくなって。
華奢な肩に、細長い指先。パッチリ二重は変わらないけれど、どこか大人びた表情。
きっと、綺麗になった彼女をみて、俺は少し怖くなったんだ。だからその面影をみて、俺は泣きそうになった。
「よく、わかったな」
「わかるよー。だって康太身長すごく大きくて目立つ上に、すごい挙動不審だったし、何より瞼の傷。――中学の頃体育のサッカーで私を庇ってできた傷があったんだもの」
「そういうことか」
「元気だった?」
「まあ」
「なんだー。私がいなくなって、毎日泣いてるかと思ったのに」
そういって悪戯に笑う彼女が愛おしくて、俺はやっぱり杏が好きだ。
「――杏」
「ん?」
「俺お前の事好きだった」
「――――ははっ、何々どうしたー?綺麗になった私に惚れちゃった?」
「……あの時、杏が告白してくれた時……冗談だなんて言ってごめん。俺、すっげー後悔した。だからもう、後悔したくない。だから伝えなきゃって思った。またお前がどこかに消えちゃう前に」
「……」
「ずっと、ずっと。俺はあの頃から、杏の事が好きだった」
「――――遅いよ、バカ」
ああ、やっぱり。手遅れだよなぁ。
「ははっ……。急にごめんな」
「何年待ったと思ってるの……?」
「……え?」
「私だってずっと、康太の事が好きだった…っ!忘れられなかったのは、私のほう…っ」
大きな瞳から零れ落ちる大粒の涙。
「本当に?」
「……これが嘘だっていうなら、どうしたら信じてもらえるの?」
「いや、」
気が付けばあたりに人はいなくなっていた。
俺は杏のか細い腕を引き寄せ、自分の腕の中に閉じ込めた。
「夢みたいで、幸せすぎて、本当に現実なのか信じられないだけ」
「……うぅっ……康太こそ、嘘じゃないの……?」
「……告白が嘘に聞こえるなら」
俺はそっ、と杏の唇にキスをした。
「これで、信じてくれる?」
頬を真っ赤にしながら頷く彼女を、俺はもう一度抱きしめた。

携帯小説・恋愛小説家兼、シナリオディレクター。(株)KADOKAWAより処女作「LOVE♡GAME」を出版し小説家デビュー。現在はNHNcomico(株)公式作家として活動中。普段は乙女ゲームのシナリオ製作の仕事をしている。